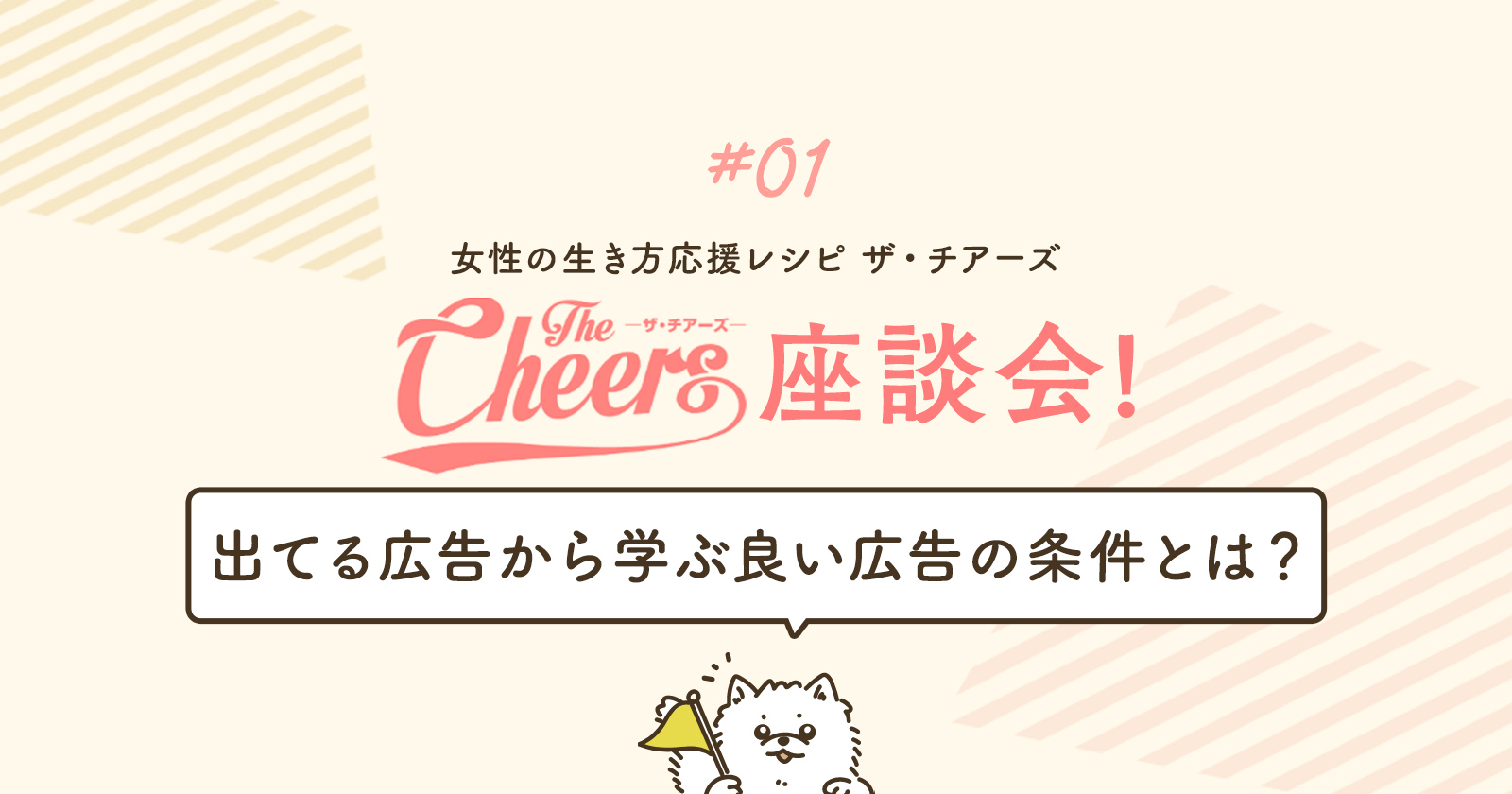
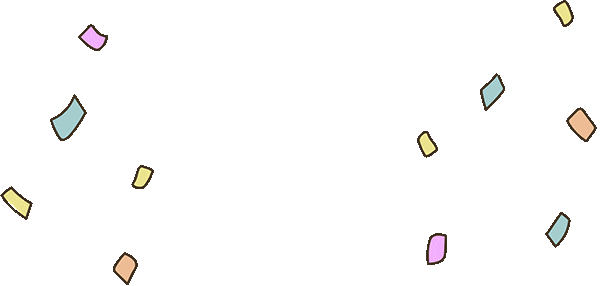
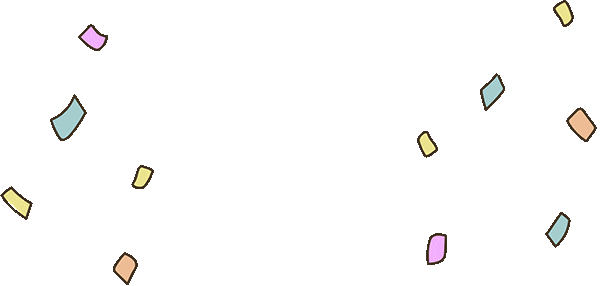
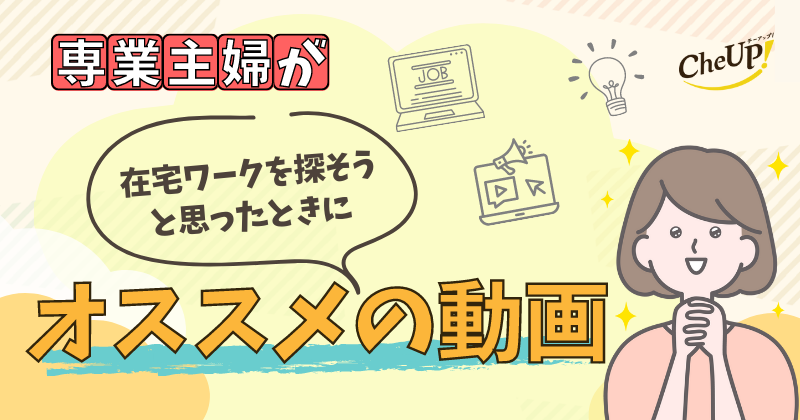
専業主婦が在宅ワークを探そうと思ったときにオススメの動画

この記事は、専業主婦でこどもが大きくなってきたので「仕事をしてみようかな」、「仕事を再開したいけど、うまくいくかな」と、迷っている方にオススメの動画をまとめました。
専業主婦になって、仕事を離れている期間が長ければ長いほど、仕事を始めることで生活環境が変わることに不安や抵抗を感じるように思います。
実は、私も結婚してから専業主婦になりました。でも、二人目を出産してから、働きたいという気持ちが強くなり、家事や育児の合間にできる在宅秘書(在宅アシスタント)の仕事をスタートしたのです。
そして今では、「思い切って仕事を再開してよかった!」と心の底から言えます。
だから、少しでも「仕事をしてみたいな」と考えている方には、この記事で紹介する動画をご覧になって、一歩を踏み出していただけたら嬉しいです。
尚、在宅秘書にご興味を持った方は、こちらもぜひご覧ください。

専業主婦がパートを始めようとする理由は様々ですが、「仕事してみたい」という気持ちに対して、ためらってしまうポイントは主に次の5つです。
私も、在宅秘書の仕事を探す前に、仕事を始めることによって、生活環境が変わること、こども達や家族に迷惑をかけないだろうかと、悩みました。
ひとつひとつ、見ていきましょう。

パートと家事や子育てを両立することは、時間やエネルギーを大きく要するため、専業主婦からパートに転換する場合、特にストレスや負担を感じてしまうでしょう。こどもが体調不良のときに仕事をすんなり休めるの?職場には理解があるの?などと、考えだしたらきりがありません。
そのような方にオススメなのが、在宅ワークです。コロナ禍でオンライン化が進み、在宅でパートのように働ける仕事が増えています。パートタイムというと、9時〜18時など会社の営業時間内に働くことを考えがちですが、在宅ワークならお子さんが寝ている朝や夜に働くことができるのです。

子育てなどで時間的制約がある場合、勤務時間や勤務日数などに制約が出てしまい、仕事の選択肢が狭くなることがあります。求人条件に、「週3日4時間以上。土日歓迎」などと書いてあれば、他の方と比べて条件が悪くなって、選ばれないのではないかと思う方もいるでしょう。
そのような場合でも、在宅ワークなら時間的な制約がなくなります。家にいながら、パートに出るよりも時間単価の高い働き方だってできるのです。まずは、どんな仕事があるのか、こちらをご覧ください。

結婚前は平凡な事務職だったので、特別なスキルなんてない。職歴や仕事の経験が少ないことは、人気の職業に応募するときには、影響することがあります。でも、応募する仕事に対して、真摯に取り組むことや、自主的に勉強をしてキャッチアップしていくという姿勢を示すことも大事です。
「経験がないから…」なんて躊躇せずに、なぜその仕事がしたいのかを考えて、熱意を伝えてみませんか。
私が経営者として採用するときは、経験があってもやる気のない人よりも、未経験でもやる気に満ち溢れた人と一緒に仕事をしたいと考えます。

仕事を始めることで、趣味や家族との時間などのプライベートの時間が減り、ときにはこどもにも我慢してもらうことがあるかもしれません。また、「今日、お茶しない?」と誘われて、気軽に応じていたママ友達との時間も、減ることになるでしょう。
人生100年時代なので、自分の人生をどうしたいのかを考えて、「今だ!」と思ったら、多少の犠牲を覚悟して、一歩踏み出してみませんか?どんな年齢でも、仕事をはじめるに遅いということはありません。

いざ仕事を始めたとしても、最初のうちはパートで得られる収入が少なく、忙しくてお惣菜を購入したり、一時保育にお願いしたりすることによって、ほとんど残らないこともあるでしょう。
そんなとき「働く意味はあるのかな?」と考えてしまいがちですが、新しい環境に慣れてくれば、徐々に手元に残るお金も増えていきます。それに、仕事のスキルやキャリアは確実に増えていくので、安心してください。
また、お金への漠然とした不安は、行動することで解消できますよ。

いかがでしたでしょうか?
動画をきっかけに、「仕事をしてみたい」、「働いてみようかな」と考えている方が、新たな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
また、「在宅でなら無理なくはじめられそう」、「在宅ワークをやってみたい!」という方は、ぜひ下記から「在宅ワークですっごく重宝されるアツアツスキル51のチェックリスト」を無料でダウンロードしてみてください。
アツアツ#01: おうちで働くなら絶対マスターするべきITスキル
アツアツ#02: あなたにピッタリな働き方を見つけよう!
アツアツ#03: 応募するときにアピールすると良いスキルとは?
ご自分にピッタリの働き方や勤務時間、効率的な家事や育児の方法を見つけることができるよう、応援しています。

この記事を書いた人
野川 ともみ